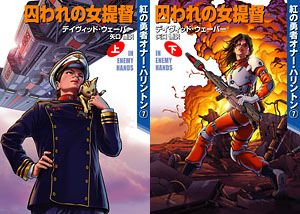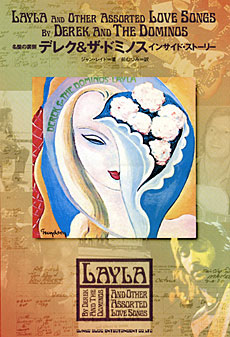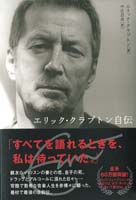原典を知れ!
今,「MATRIX - Reloaded」がヒット中ですわな.
現在の映像テクノロジーがあるからこそ実現できた映画です.
まだ観てませんが,前作も確かに“映像的には”,面白かった.
そこは,動かしがたい.
ただし,SFとしては,そんなに新しいものじゃない.
ジャンル的には,20年ほど前にウィリアム ギブソンが「クローム襲撃」や「ニューロマンサー」,
「モナリザ・オーヴァードライヴ」で始めた,“サイバーパンク”と呼ばれるもの.
具体的には,現実空間と電脳空間の往来が舞台.
別にケチ付けるわけではないですが,前作を観たときも「そんなに騒ぐほどのもの?これ?」って思った.
「やっと,サイバーパンクを映像化できる技術が開発されたか」くらいなもので.
この映画が話題にされるときに“サイバーパンク”という言葉が全く出てこないだが,どういうことだ!?
映画とSF小説の間に“映画=オシャレ×SF小説=オタク”とか差別的概念が存在するんじゃないのか!?
ハッキリ言って,小説読む方が文字だけで情景を想像しなければならない高い知的能力を要求されるし,
映画館のスクリーンよりもイマジネーションのスクリーンの方が遙かに巨大なのだよ!